
平安時代
源頼朝 1147~1198
以仁王が平氏追討を命じると、源頼朝は挙兵を決意し当山に平家討伐を祈願します。
成田山とのご縁
本格的な武家政権である幕府を開いた武士。
源頼朝の祖父である源頼義が、成田山新勝寺の本堂を再建していることから、源氏と当山の関係は深いものがあります。1180(治承4)年、後白河法皇の皇子である以仁王が平氏追討を命じると、源頼朝は挙兵を決意し当山に平家討伐を祈願します。その後、平氏を滅ぼした頼朝は鎌倉幕府を開き、征夷大将軍に任命されます。日本の三大仇討ちの一つである「曽我物語」で有名な曽我兄弟の図が成田山霊光館に所蔵されていますが、この兄弟を捕えて罰したのも源頼朝です。

室町時代
道誉上人 1515~1574
道誉上人が成田山で行ったとされる100日に及ぶ断食修行の図が当山に所蔵されています。
成田山とのご縁
徳川家の菩提寺として有名な増上寺の第九世住職。
道誉上人が当山で行ったとされる100日に及ぶ断食修行の図が成田山霊光館に所蔵されています。満願成就の日、上人の前にお不動さまが現れ、剣をふるって上人の喉を破るのですが、この日を境に上人は数万の経文を一瞬で暗記できるようになります。この剣は、お不動さまが右手に持つ利剣で、智慧の象徴です。道誉上人は、その後、増上寺の第九世住職になり人々から名僧と慕われました。

江戸時代
海保甲斐守三吉 生年没年不明
刺された海保甲斐守三吉の前に、制咤迦童子が現れ、蘇生させたと言います。
成田山とのご縁
江戸時代初期の武将で成田にあった寺台城の城主。
海保甲斐守三吉は、諸堂伽藍の建立や絵馬堂の奉納、またかつて白木造りだった当山の2つの仁王像を、所願成就のお礼として、朱塗りにして仁王門に奉安したというほど、非常に信仰の深かった人物です。合戦の最中に刀で刺された海保甲斐守三吉の前に、お不動さまの脇におられる制咤迦童子が現れ、蘇生させたという霊験記が残っています。

江戸時代
徳川光圀 1628~1700
徳川光圀公が記した「甲寅紀行」には、公が成田山を参詣したという記事があります。
成田山とのご縁
水戸黄門で有名な徳川御三家の一つ水戸藩の第二代藩主。
徳川光圀が房総地方を旅行した際の「甲寅紀行」には、光圀が成田山新勝寺を参詣したという記事があり、御本尊不動明王の御尊像に対して「極めて奇なる」と表現した記載もあります。また、当山中興の祖である照範上人が徳川光圀の子息だったのではないかとする伝承など、水戸藩と当山とが幕末まで非常に親密な関係を続けた理由について、散見する事ができます。

江戸~明治
二宮尊徳 1787~1856
二宮尊徳は、人びとを救いたい一心で、当山の21日間に及ぶ断食修行を成就させます。
成田山とのご縁
江戸時代後期の思想家、主に農民たちの生活向上につとめた。
二宮尊徳は、1787(天明7)年に相模国、現在の小田原市に生まれました。利根川水路の建設工事の立案など、生涯をかけて農業政策に取り組んだ人物です。尊徳は、成田山新勝寺のお不動さまを深く信仰した人物です。世の貧しい人びとを救いたい一心で、当山の21日間に及ぶ断食修行を成就させ、その後、農民たちの生活向上のため、多くの疲弊した農村の復興に寄与しました。
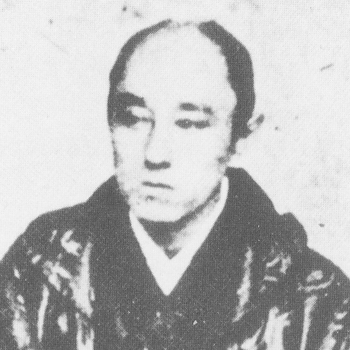
江戸~明治
山内容堂 1827~1872
山内容堂公が病床につかれた際、当山の7日間に及ぶ平癒祈願の祈祷の結果、快方に向かったと言います。
成田山とのご縁
江戸時代後期の土佐藩主、幕末の四賢侯と呼ばれ活躍した大名。
成田のお不動さまを深く信仰した山内容堂公は、毎年1・5・9月に祈願し大護摩を修行い、代理の方を通じてお札を山内家に持参させていました。山内家の家宝の中から大変貴重な多数の能面と能衣装を寄進され、当山で今も宝物として所蔵しております。明治の時代になり病床につかれた際、当山の7日間に及ぶ平癒祈願のご祈祷の結果、快方に向かったという御霊験が伝わっております。

江戸~明治
山岡鉄舟 1836~1888
山岡鉄舟は、明治天皇が当山に行幸された際に、宮内少輔として随行しました。
成田山とのご縁
幕末の三舟と称される明治維新の功労者、無刀流を創始した剣の達人。
明治天皇の側近として仕えた山岡鉄舟は、天皇からの信任を厚く受けていました。1882年(明治15年)に明治天皇が、当山に行幸され、ご宿泊された際にも、宮内少輔として随行しました。書家としても第一級であり、今でも成田山の明治天皇行在所の傍室に掲げてある「不動心」と書かれた書は、見る者の心を打つ迫力ある筆跡です。
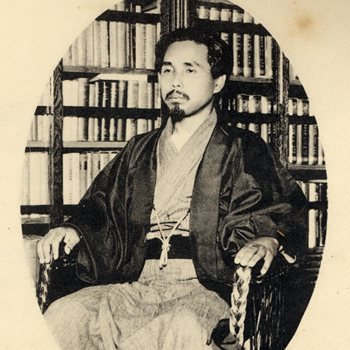
明治~昭和
倉田百三 1891~1943
倉田百三は、病弱な体で不可能と言われた当山の21日間の断食水行を行いました。
成田山とのご縁
大正、昭和初期に活躍した文学者、小説家、評論家。
1891(明治24)年に生まれた倉田百三は、若いころから病身で、入退院を繰り返しながら創作活動をつづけます。人気作家になってからも、作った短歌にお不動さまへの熱烈な信仰を吐露しており、病身の肉体的苦痛が大きな悩みになり、救いを求めていた事が窺えます。この悩みに打ち勝つため、百三は病弱な体であえて、21日間の断食水行を行い、その後の超人的な創作活動の原動力を作りました。

